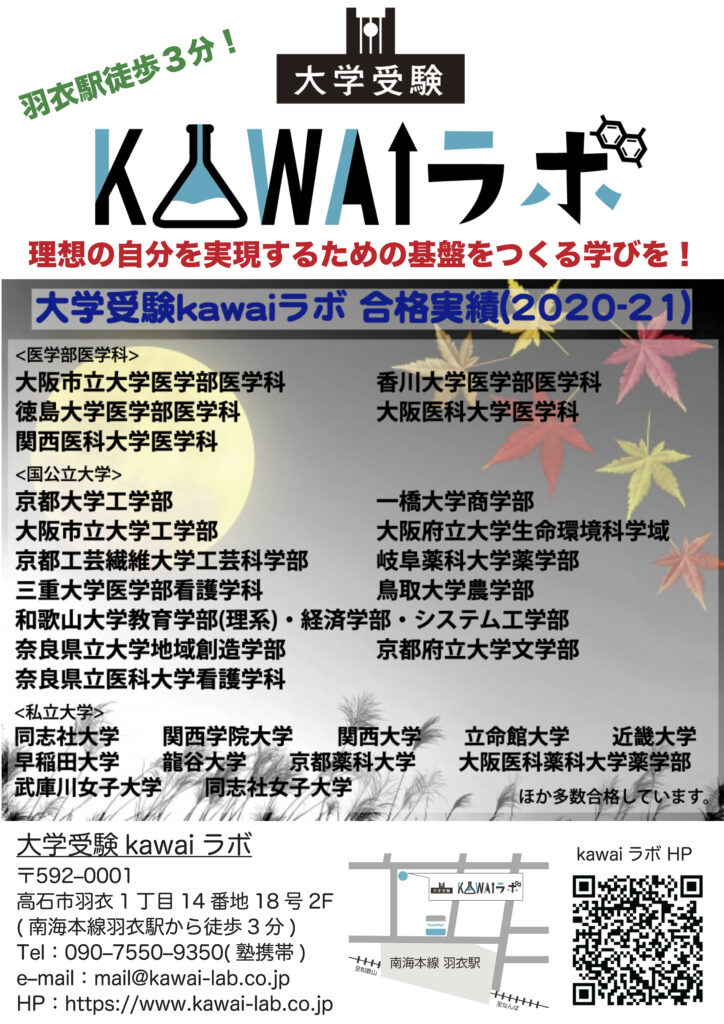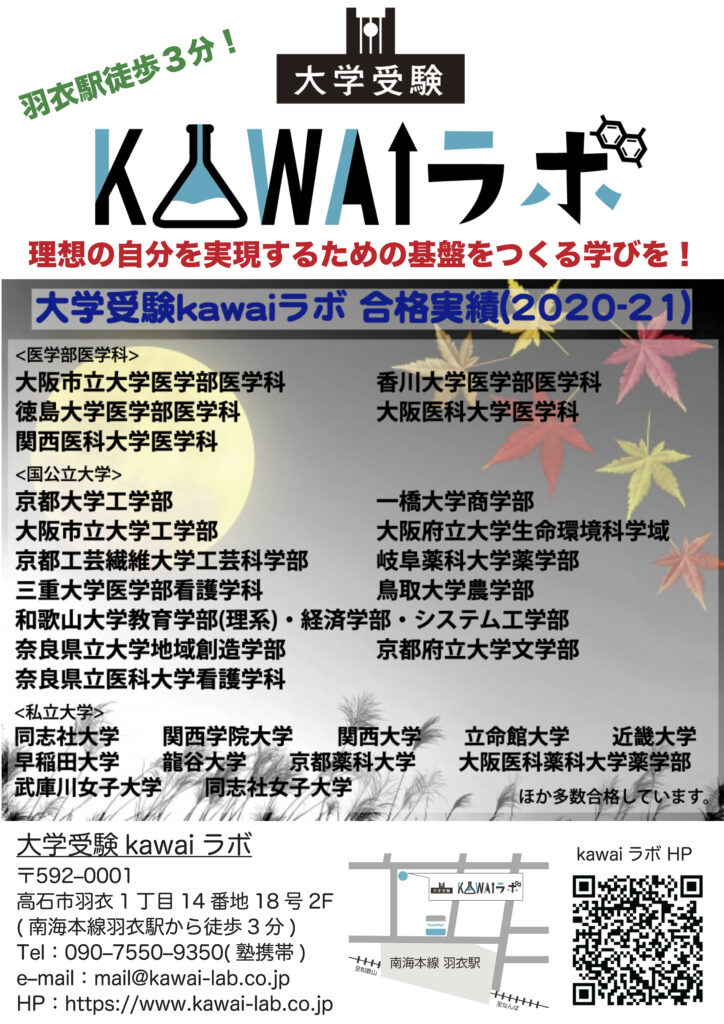こんにちは、大学受験kawaiラボの河井です。ついこの間まで袖をまくって教室でやっていた、というのにすっかり冬めいてきて、鍋物や熱いラーメン・うどんが美味しい(こらそこ!いつもラーメン食べてるでしょとか言わない!)時節になってまいりました。通常の入塾に加えて、この時期らしい以下のようなプランを出しますので、この機会に大学受験kawaiラボをご検討ください。ご相談などはこちらからお願い致します。
① 高1・2・中学生対象「冬から頑張る人向けプラン」
現在期末テスト前で必死!になっている高1・2年生の方とその保護者さま向けのプランです。だんだん内容が難しくスピードアップしてきたな…という高1、期末テスト過ぎたらもう入試まであと1年だよね…と思う高2の方に、期末テスト後、これまでの振り返りから始めて年始からの学習にシームレスに移行してもらおうというものです。テスト明け(遅くとも12/15になると思います)から1ヶ月間、休み明けの課題考査までをカバーする形で通い放題形式で来て頂こうというものです。テスト直し、冬休みの課題の消化から始めて、必要に応じた補強や高2生だと受験勉強の入り口にあたるところをやってもらおうというものです。
<募集要項>
・期末テスト後の日程で1ヶ月間通い放題形式
・授業料:高1生・高2生とも44,000円(税込)、中学生は33,000円(税込)
・その後も大学受験kawaiラボで継続して頑張っていこう!と思って頂いた場合には1月分の授業料は半月分で計算させて頂きます。(+諸経費等)
② 受験生対象「過去問添削指導プラン」
これから追い込みの時期に入っていきますが、やっていて悩ましいと感じるのが赤本などの過去問を使っての学習になると思います。過去問研究は秋まで培ってきた基礎学力の上に癖だとか形式など慣れの要素を乗せることで自力が効果的に発揮できるようになるための最後のピースだと考えています。その過去問研究の効果を高めるべく、そのやってもらった過去問に添削指導をし、また、やり直しまで含めてオンライン(Slack)のやり取りでサポートしていこうというものです。
<募集要項>
・開講科目は数学(文理とも)・化学・物理・生物・英語です。
・オンラインツールであるSlackに問題と答案をアップ(LINEみたいに使います)してもらい、添削指導及びやり直しのやり取りを行います。
・提出とやり取りの回数制限はございません。
・費用(1ヶ月あたり・税込):1科目11,000円、2科目20,900円、3科目30,800円、4科目40,700円(振込手数料はご負担ください。)
まもなく受験を迎える人/これから受験生になっていく人、どちらのサポートもしっかりしていきたいと思います。ご興味をもって頂いた方・ご相談されたい方はこちらのフォームからお問い合わせくださいませ。なお、以下には通常の講座の募集要項も掲載しますので、こちらにつきましてもご検討いただければ幸いです。
大学受験kawaiラボ募集要項
中学生〜浪人生まで、大学受験を念頭に入れて勉強をしていきたい人が対象です。初回面談時に現状を知りたいので成績資料(学校成績・模試成績)はお持ち頂きますが、入塾テストはございません。ラボの方向性をご理解頂いた方すべてに門戸を開いております。
指導形式:集団個別指導と言われるものですが、要は個別対応です。
○得意
・大学受験をがっつりと頑張りたい
・高校数学/物理/化学/生物/国語/英語をしっかりとしていきたい
・中高一貫校で高校数学の4step、サクシードや青チャート、フォーカスゴールドをなんとかしたい
・たくさん授業を聞くよりも自分が解いて身につけた
○不得意
・高校入試の内申点対策(難問をじっくり考えるのは得意ですが、中学の定期テスト傾向を掴んでいるわけではないので)
・短期スパンでのテストで結果が欲しい(対策で押し切るタイプの指導をしないので)
・授業らしい姿を求めている(自分ができるようになる、を主眼にしているのでたくさん喋る授業を求める人とは相性がよくない)
授業料:
高3・浪人:月55,000円(税込)
高1・2:月44,000円(税込)
中学生:月33,000円(税込)
諸経費:
入塾金:16,500円(税込、紹介の方は5,500円引き、兄弟姉妹の方は0となります。)
年間維持費:19,800円(税込、3月からで入塾月に応じて計算します)
長期休暇期間中の追加料金:
高3・浪人:夏季55,000円(税込)、冬季55,000円(税込、12月〜受験終了までの分です)
高1・2:夏季33,000円(税込)、冬季なし、春季:11,000円(税込)
これまでに掲載されていた金額を法制上総額表示にしたため、高くなったように見えますが、外税分を入れている形になっていますので、実際には変更はございません。ご検討いただいた方は
https://kawai-lab.co.jp/contact.html
よりお問い合わせいただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
オンライン個別指導(zoom)募集要項
<要項>
・週1コマ80分、月4回。時間帯は平日土日夜21時以降、土日午前、平日日中で相談の上。
・Slackにて質問対応・添削を受け付けます。
・費用(月額・税込):1コマ26,400円、2コマ48,400円、3コマ、66,000円
・前月末振込でお願いします。(振込手数料はご負担ください。回数が違う月は回数に合わせて変動します。)
オンラインが生きるタイプは1科目単位からできる個別指導ではないかな、と思っています。それもめいいっぱい講師側がしゃべるオンラインだけでなく、直接話す時間と添削のやりとりによるカタチを大学受験kawaiラボは提案したいと思います。そう言った意味では80分1科目、という進め方もあるでしょうし、1週間の学習の総括や次の指針立てをコマの中で行い、具体的な課題のあれこれは添削と課題のやり取りで進めることも可能です。また、フルパッケージの予備校などの補助や赤本のやり直しや解説に特化するなど、オーダーメイドで指導を構成することができます。そういった自由度の高いオンラインをひとつ提案したいと思います。お問い合わせはこちらからお願いいたします。